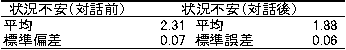
社会性の獲得に及ぼす会話の影響
実験
206qa90 江夏泰二郎 (Taijirou Enatu)
要約
大学生を対象とした心理実験、研究は数多くある。大学生は一般的に将来の自己を確立するための準備期間であるといえるが、就職を控え自分が進む道を模索している時期でもある。多くは企業への就職を希望していることであろう。しかし企業においては現在メンタルヘルス上の様々な問題が噴出している現実がある。それは就業形態の大きな変化がひとつの要因であるとも考えられる。
特に1997年に本格化した不況を背景とした企業側の経営指針の転換によるコミュニケーションの問題、個別作業の増大は目に見えて増加している。その他VDT作業の増加もメンタルヘルス上の問題と関連している。いずれも就業形態の変化により余儀なくされたコミュニケーションの希薄化を生み出した。そして企業においてコミュニケーションの希薄化はメンタルヘルス上の問題へと繋がっている。それらは早急に解決する必要がある。というのも1998年を皮切りに自殺者数は増加ついに3万人を突破した。その後8年間の間労働省や厚生労働省より「心の健康づくりを策定すること」など企業側に対して警告を促しているにもかかわらず、依然として改善傾向にない。そしてその内訳においてその3割が就労者による経済、生活上の問題と考えられる。これらの問題を考える上で心について学ぶ心理学科の生徒としては「心の問題」は見逃すことのできないことである。
そこで今回は実験を通して、コミュニケーションの問題に焦点にあてることとした。実験は二人一組による相互の会話を人工的環境においてつくりその前後で「社会的望ましさ」や「個人的親しみやすさ」といった「他者の目」を考える社会性が会話によってどう変化するか、またそれらの社会性は日常の不安感(心の問題を引き起こす要因)の軽減とどう関係しているのかを調べた。また、個人的な性格特性を事前に測り、神経症傾向にある対称に与える会話の不安感の低減の影響を考えた。
問題
昨今の社会とりわけ企業において問題となっているのは対人的なコミュニケーション不足による就労形態の変化である。それは1997年の武田薬品の個人成果主義の導入に始まる。個人成果主義の導入は、就業における個室化問題を生み出した。現在の就労状況は1997年以前とは大きく変化しそれまでの人間関係を重んじる「場」から「個人で働く労働スタイル」へと変化した。「集団でひとつの目標を対象とする」傾向はなくなり「個人」での仕事が増えているのである。
それは企業リスクのトップ項目であるメンタルヘルスの問題にも深く係わっている。個人成果主義の導入の背景にはもちろん不況の打開がある。1997年の山一證券の倒産、1998年の日本長期銀行の破綻からはじまる金融危機が背景にある。しかしこういった個人成果主義の導入は2002年までは、一時的なカンフル剤としてある一定の効果を示したものの、それ以降は欧米と日本の社会的背景の差からの無理がたたった為か負の遺産として個室化現象、対話欠乏症、評価不信感、自己不確実、格差社会、同僚への劣等感、コンプライアンス萎縮、早期離職等の問題へと繋がった。
個室化現象とは上述したように「場」から「個」への変化であるが、欧米に習った個人成果主義が大きく関係している。これにより日本的経営がそれまで重んじてきた「場」の論理、人間関係を重んじるという事が否定された。成果主義においては仕事が切り分けられ個人に割り振られる。そのパフォーマンスを測り、評価が下される。「場」の論理からいきなり個人単位の仕事と評価の仕組みにさらされたためである。そして個人のキャリアが重要視され仕事の個室化現象が進んでいったのである。その中で就労者は「場」に従って仕事をしてもけっして安心できないことを、身をもって知っていったのではないか。成果主義のもとでは1人1人が断片的な仕事をするので周りの同僚との仕事の関係性が分かりにくくなる。特に仕事がうまくいかず忙しくなると「人間関係よりも自分の仕事をやり通す事が大切だ」となり同僚との人間関係も悪くなってしまう。しかしこの事が個人の性格の特性かといえばそうではない。社会構造の変化の結果起こった必然的なことであるように考えられる。
そのためこのような事態で組織益を考えると自分の仕事をやりぬく事が大切であるのだが、躊躇なくそれができない就労者は相手益のことをどこかで考えてしまう。多かれ少なかれ葛藤(コンフリクト)状態におちいるがこれもまたメンタルヘルス上良いこととは考えにくい。レビンが葛藤のパターンを3つに分類しているが回避-回避型の葛藤状態に慢性的に陥ることとなるからである。要は板ばさみの状態である。相手益ばかりを優先させると精神的に良くない状態が継続する。その打開には「交渉」といったことが必要になってくるのではないか。組織益を優先させれば自分益、相手益が後回しになってしまう、自分益を優先させれば組織益、相手益が後回しになってしまう、相手益を優先させれば自分益、組織益が後回しになってしまう。「交渉」においてどの益を優先させればよいか。自分益を優先させる事が一番なのではないか。自分益を優先させればならない。自分が充実した生活を送れてこそ、組織益や相手益を考える事ができるようになる。自分益を後回しにすると、メンタルヘルス上も良くない。交渉の手法としてはまず小さな要求からはじめ、徐々に要求を大きくしていく「フット・イン・ザ・ドア」、始めに大きな要求を行い、相手が断った時点で小さな要求を出していく「ドア・イン・ザ・フェイス」、相手が受け入れやすい要求を行い相手が受け入れた時点で付加的に要求を行う「ロー・ボール」などの心理的なテクニックが知られている。個人単位で働く環境のなかでこういったテクニックも考慮にいれてなるべく自分益を確保することもメンタルヘルス上、有用なのではないか。
次に対話欠乏症だがこれは成果主義の導入→個室化現象→対話欠乏症という一連の流れによるもの。評価不信感も一連の流れにより発生したメンタルヘルス上のリスク要因のひとつである。これは、以前のようにひとつの目標に対しての取り組みから個人単位での断片的仕事の増加により、他と係わりながらの仕事が大幅に減少しそれにより人からの評価を受けることもなくまた自分からの評価を下すこともなくなったことによる。そのため日常的なコミュニケーションの希薄化をうみ自分の自分に対する評価と他がくだす自分の評価の間にギャップがうまれる。
自己不確実は1997に始まる金融危機、不況と大きく関係しており、企業界全体が将来への希望を持てなくなっておりその反面仕事量だけは増大して言っている。それによる将来への不安である。次の格差社会もやはり成果主義の導入に起因している。成果主義を導入することで、仕事の意欲はバブル崩壊から下がり始め1998年に底をうったが成果主義の導入が本格化した1999年から上昇を見せ始めた。しかしそれも一時的なものでやはり日、欧の社会背景の差もあってか2002年をピークに下降している。成果主義は職場内に競争を持ち込むことによって個人のパフォーマンス生産性が高まり、会社全体が活性化するという考えを基本にしている、しかし現在、実際には競争することによって不安になり、劣等感を持つ人が急増する流れになっている。同僚への劣等感もこのことから生まれている
コンプライアンス萎縮は過度なフォームによる就労者の締め付けと考えられる。コンプライアンスは本来社会からの要望に応え、経営資源を効率的に活用して企業価値を最大化し、適正に事業目的を実現する組織体制そのものを意味している。一昔前ならばネジ一つ買うのに管理の手続きなどは不要であったが、今はそうは行かない。何かひとつの行動を起こすにも数枚もの書類で会社側に申請し会議によるその答えを待ちやっと許可が下りるのである。コミュニケーション不足と直接の関係はないように見えるが、問題は管理者や経営側が「欧米ではあたりまえだから」といったことで済ませ就労者に対しなぜ、そういった何十もの手続きが必要なのかという説明が十分になされていないことにある。就労者は頭で分かっていても腑に落ちないとより強いストレスを受けてしまう。これら一連の問題はメンタルヘルス上のリスクとされ、全体的に見ると社会背景の変化によるコミュニケション不足の影響が見て取れる。
「社会的親しみやすさ」、「個人的親しみやすさ」はメンタルヘルス問題のリスクとしての対人的コミュニケーションの改善の鍵になるであろう。またその2点が、対話によって良好かつ円滑になれば結果、上述したような問題の改善に繋がり企業の就労者の心の問題のマネージメントに繋がるであろう。
目的
現在の企業においては問題で述べたような対話欠乏症、評価不信感、自己不確実、格差社会、同僚への劣等感、コンプライアンス萎縮、早期離職等から就業者は神経症的傾向に必然的になってしまっている可能性がある。またそれ以外にもIT(情報技術)化、文章の入力での使用増加、専門性を要する仕事での活用、プレゼンテーションでの使用、コミュニケーションツールとしての活用に伴う職場でのVDT(Visual Display Terminal)作業の増大に就労者はそのストレスから神経症的傾向になる。そこで神経症傾向を持つ対象群が10分間の会話の前後でコミュニケーションの改善に繋がるであろう事を明らかにするため本実験を行い検証を行うこととした。
方法
本実験には46名(男15名、女31名)が参加し、ランダムに2人1組でペアを組み合計23組が参加した。使用した尺度は、事前調査においてMPI特性尺度、コミュニケーションスキル尺度、コミュニケーション参与スタイル尺度、STAI特性不安尺度、特性シャイネス尺度、対人恐怖尺度、直前アンケートにおいてSTAI状況不安尺度、多面的感情状態尺度、関係性を測定する項目、特定形容詞尺度、直後アンケートにおいて多面的感情尺度、STAI状況不安尺度、特性形容詞尺度、自分の評価を測定する4項目、相手の評価をする4項目、満足度を用いた。本論では対人恐怖尺度、STAI状況不安尺度、を用いた。
始めに実験参加者全員に対して事前調査を行った。次にランダムにペアを作りそのペアごとに別室に案内し直前アンケートに回答を求めた。そしてペアを実験室に案内し対話形式で各ペアで10分間自由に会話をする会話実験を実施した。会話の始まりと終わりの合図としてベルを鳴らし教示を行った。実験終了後会話ペアを再び別室に案内し、直後アンケートに解答を求めた。会話実験の教示内容は以下の通りである。
会話実験教示文
「こちらにおかけください。」
「椅子は動かさないでください。」
「今から10分間自由に会話をしていただきます。」
「何を話してもかまいません。」
「会話の始めと終わりに1回ずつベルを鳴らします。」
「最初のベルが鳴ったら話し始めてください。」
「10分後終わりのベルを鳴らします。」
「終わりのベルが鳴った後は一切私語はしないでください。」
「では始めますので、ベルが鳴るまでお待ちください。」
実験終了後ベルの後に入室し以下の教示を行う。
「これで実験は終わりです。」
「この後、2回の126へ移動して質問紙に解答してもらいます。」
「移動中の私語は決してしないでください。」
「ご協力ありがとうございました。」
結果
神経症的傾向の平均は1.42、SD(0.08)対話直前における状況不安の平均は2.31、SD(0.07)個人的親しみやすさの平均は4.90、SD(0.18)社会的望ましさの平均は4.86、SD(0.12)対話直後における状況不安の平均は1.88、SD(0.06)個人的親しみやすさの平均は5.7、SD(0.15)社会的望ましさの平均は5.04、SD(0.12)であった。
Table 1.会話前後での不安状況の変化
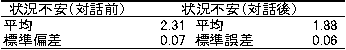
Table 2. 会話前後での個人的親しみやすさと社会的望ましさ
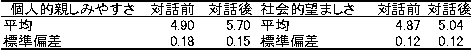
状況不安(神経症傾向低群)は個人的親しみやすさと強い負の相関を示した(r =−.43、P <.01)。状況不安(神経症傾向低群)は社会的親しみやすさと相関関係を示さなかった(r =−.12、P =n.s)。状況不安(神経症傾向高群)は個人的親しみやすさと相関を示さなかった(r =−.08、P =n.s)。状況不安(神経症傾向高群)は社会的親しみやすさと相関関係を示さなかった(r =.06、P =n.s)。
Table
3.会話直前の状況不安と特性形容詞との相関
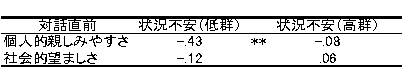
Note.**P<.01,*P<.05,+P<.10
Table
4.会話直後の状況不安と特性形容詞との相関
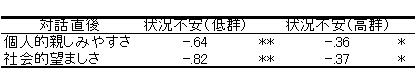
Note.**P<.01,*P<.05,+P<.10
状況不安は会話によって減少した。また、個人的親しみやすさと社会的な望ましさは増加した。
状況不安(神経症傾向低群)は個人的親しみやすさと強い負の相関を示した(r =-.64、P <.005)。状況不安(神経症傾向低群)は社会的親しみやすさと強い負の相関を示した(r =-.82、P <.005)。状況不安(神経症傾向高群)は個人的親しみやすさとやや負の相関を示した(r =-.36、P =<0.2)。状況不安(神経症傾向高群)は社会的親しみやすさとやや負の相関関係を示した(r =-.37、P <0.2)。また会話前後の相関の変化量を見ると神経症傾向低群での状況不安と個人的親しみやすさは.21状況不安と社会的望ましさで-.7神経症高群での個人的親しみやすさの相関は.28社会的望ましさで-.43の変化量が観られた。
考察
状況不安は会話によって緩和された。また、個人的親しみやすさと、社会的望ましさはペアを組んだ対象に対して増加した。
対話直前の状況不安は、神経症傾向低群で社会的親しみやすさとのみ、相関を示した。しかし会話直後には、状況不安は、個人的親しみやすさ、社会的望ましさいずれも相関を示した。また相関の変化量で一番大きかったものは神経症低群での社会的望ましさで-.70であった。
これはどういったことを意味しているのかというと、会話の有用性である。個室化現象、[場]から「個」への変化は上述してきたが、会話がコミュニケーションの促進の要因であろうと考えられる、相手に対しての、個人的親しみやすさ、社会的望ましさを増加させている。就業環境に限っていえることだが、社会背景による個人成果主義の導入による様々な問題の噴出、そしてそれらによる企業のリスク要因で上位に挙げられるメンタルヘルス問題が生まれたことは不況などの背景を考慮すれば、仕方のなかったことなのかもしれないが、これを打破する鍵が、会話にあることを実験結果は指し示した。
相関を見ると、会話の前には状況不安は神経症傾向のない低群において個人的親しさのみ負の相関を示していたので状況不安は個人的親しさとのみ関連を示していた。つまり状況に不安を感じていなければいないほどペアの対象に対しての感情が増し、個人的な親しみを増していたと考えられる。他の社会的望ましさは、神経症傾向高群においてもまた神経症低群においても関連性は見出せなかった。コミュニケーションをとるために、個人的親しみやすさは、必要不可欠である。神経症高群がいずれとも不安と相関を示さなかった理由のひとつには、不安がある一定の値を超えるとその大小に係わらず、個人的親しみやすさや、社会的望ましさが常に希薄だからではないか。
しかし、会話後には神経症傾向高群、低群いずれの状況不安も個人的親しみやすさ社会的望ましさと負の相関をしめした。この事は、対話がペアを組んだ対象に対して会話によって何らかの感情をもちそれが個人的親しみやすさや、社会的望ましさといった「他」(この場合ペアの対象)に対して親しみを覚えよく見られたいという相手を意識する感情が神経症傾向高群においても低群においても生まれたためではないか。このように会話の後には、相手を意識する事が分かった。コミュニケーションにおいてその増加を望むためには、会話が効果的であることが立証された。低群における社会的望ましさが会話の前後で最も大きい変化量を見せた事は、確実に他の眼を意識しだしていることを意味している。社会的望ましさは、神経症傾向高群においても低群においても個人的親しみやすさと比べると、大きく変化していることが分かる。相関の変化量が最も大きかった神経症傾向低群における社会的望ましさは、会話によって会話の対象を意識するようになる度合いが一番強いということである。また、以上のことは逆に考えると会話の貧困化は相手との親しみやすさや社会的望ましさがなくてもあまり不安と感じないといこともいえる。
しかしいずれの値も会話直後に不安が減ることにより増加しているので、やはり不安の低減にはコミュニケーションのための個人的親しみやすさや、社会的望ましさは必要といえるだろう。またTable.1より会話後に状況不安が減少していることからも会話はコミュニケーションをとるために不安を軽減させる効果があるといえる。
こういったことを考えるとやはり本実験の目的である会話がコミュニケーション問題の改善に繋がるのではないかとの仮説は支持された事が分かる。またその必要性についても分かる。1990年後半から現在まで色々なメンタルヘルス上の問題が噴出し、多くの企業がその解決に頭を悩ませていたのも事実であるが、やはり欧米に倣った成果主義は、日本においてそのまま導入することには無理があり、その結果起こったメンタルヘルス問題に繋がるような、個室化現象などの問題は企業にとって望ましくないのである。もちろん企業リスクはそれだけではないのだが、2002年から2006年までの就労者を対象とした調査でも心の問題は増加傾向にあると答えた企業が、増化傾向にあること、旧労働省時代から国の側がメンタルヘルスに対する取り組みへの警告を度々だしていることなどを考えると到底無視できる問題ではない。そこで本実験で行われその仮説が実証された会話とコミュニケーションの関係を明らかにできたことは非常に有用であったのではないかと思う。
本実験ではコミュニケーションが不安症状を低減させ、コミュニケーションを促すきっかけとなるであろう社会的望ましさや、個人的親しみやすさを容易に増加させる事が分かった。経営にこだわってとった企業側の策が個室化現象、対話欠乏症、評価不信感、自己不確実、格差社会、同僚への劣等感、コンプライアンス萎縮、早期離職等の問題へと繋がったが、少しの心がけの会話がこれらの問題緩和に繋がることを期待したい。
久留米大学心理学科レポート集に戻る
心理学の話に戻る