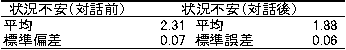
将来についての自己記述と自己概念
実験日時:2007年12月14日 P.M.3:00−5:00
206qa90
江夏 泰二郎
[目的]
人は一般的に将来のことをあまり明確に考えずに生活している。大学時代は青年期でありいろいろな経験を通して将来を見出す時期であり自我同一性を獲得、確立する時期である。将来の展望を描く重要な時期である。将来の展望については曖昧にこうありたい、こうなっているであろうとの期待、予測を漠然と持っているもののやはり自我同一性確立の時期でその内容はやはりぼやけている。
そこで展望地図(方法にて詳細は記述)を使用することにより将来に対する期待、予想がはっきりしてくるだろうとの予測の元に本実験を行った。
現在、過去と関連づけない将来記述をした場合(ベースライン)時の尺度得点と関連付けたときの将来展望を行った場合(ワーク後)の尺度得点に差があるかどうかを検証した。
[方法]
文学部心理学科2年各人番号を振り割って実験を行った。最初に将来記述(出来事法)に自分の将来起こる出来事を記入した。内容は予想、予定、計画、期待、目標、など。記入欄は20個まで。次に2つの尺度、SOC(Sense of coherence)(13項目 91点満点),時間的展望体験尺度(4因子からなる5件法) を使用し、3人1組でのグループで質的データの収集話し手1名、聞き手1名、記録者1名3人の役割を交代しながら録音、記録していった。付箋3色を使用し青(現在の自分)黄(過去の自分)ピンク(未来の自分)を使用し時間軸にそって過去から未来までを出発から到着までに見立てて展望地図を作った。
[結果]
SOCは1回目平均51.32、2回目平均54.39,t(21)=-2.13,P<.05で有意差があった。
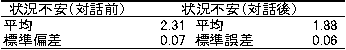
Note.**P<.01,*P<.05,+P<.10
現在の充実は1回目平均3.48、2回目平均3.68でt(21)=-2.17, P<.05で有意差があった。
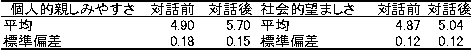
Note.**P<.01,*P<.05,+P<.10
目標の変化は1回目平均2.95、2回目平均3.3.5でt(21)=-3.80, P<.01で有意差があった。
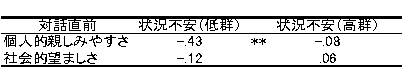
Note.**P<.01,*P<.05,+P<.10
過去の受容の変化は1回目平均3.60、2回目平均3.81でt(21)=-.138,P= n.sで有意差は見られなかった。
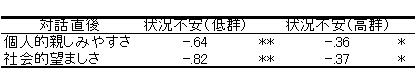
Note.**P<.01,*P<.05,+P<.10
希望の変化は1回目平均3.81、2回目平均3.86でt(21)=-.082, P=n.sで有意差は見られなかった。
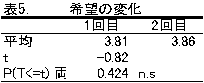
Note.**P<.01,*P<.05,+P<.10
各項目平均はいずれも上昇傾向にあった。
[考察]
SOC、現在の充実、目標、はいずれも有意差があり変化していることが立証された。過去の受容、希望は有意差が見られず変化しているとは立証できなかった。
しかしいずれの値も上昇傾向にあり将来の展望地図を書くことによっていずれの項目に関しても感心興味がわきいずれの人の意識もおおきく変化し意識を持つことが分かった。展望地図は過去から未来への流れだが、普段うっすらと意識しつつもそれが具体的な展望図としてビジュアル化したことにより意識水準が上がったのであろう。時間的展望尺度で測るものがその人の見通しであること、SOCがストレス対処、健康保持能力としての首尾一貫性を考慮した尺度であることを考えても明らかである。
聴き取りシートから考えられることは、過去、現在、未来の項目をカテゴライズし、時間軸に沿って関連づけることによって関連付けなかった時は意識していなかったものがビジュアル化することによりそれらが明らかになってきたのではないか。未来の実現性は、関連付けを行ったときのほうが現実味を帯びていたやはり文章のみでの表現では考え付かなかったことがビジュアル化することによって新たな「きづき」を促したのであろう。
展望地図の過去、現在、未来のつながりは、趣味、性格、健康、であったがやはりそれはビジュアル化して自分でもその無意識の部分に改めて気づかされた。過去から見て現在は性格を意識していることが分かりこれもビジュアル化して初めて自分で気づかされた。将来から見ての現在の位置づけは、家族のことを現在は意識していなかったがこれから両親が老化していきいやがおうにも意識せざるを得ないということであろう。現在に過去は生きているかだが、生活が以前は非常に不規則だったのが現在では規則的になっているこれは健康被害を受け健康に対するいしきが強くなったということであろう。自分にとって重要なところは、やはり数の原理でいえば性格に関する付箋の枚数が圧倒的に多かったことからすると性格に関しての(内面への)関心が高まっているということであろう。総合した感想として、展望地図を用いないときの自分の意識のこと。普段生活していてこれからのことは考えていなかったが、展望地図によって時間の流れが見えてこれまでより将来への意識が高まった。あまり将来のことを危惧し過ぎてもよくないのかもしれないがこれからの将来のことで迷った時は簡易的にでもいいので展望図を描いてみると現状にこだわりすぎて立ち止まっている自分の打破や、将来への意識が高まるのではないか。